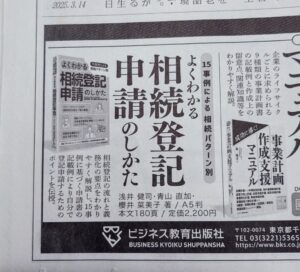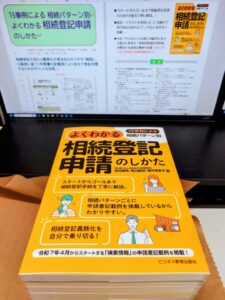いよいよ相続登記義務化が始まりました。
テレビや雑誌、インターネットや広告で相続登記の特集が組まれ、周知が図られています。
当方でも、相続登記の相談、対応を通常より力を入れて対応させて頂いております。
多くの方にとって、なかなか普段馴染みのない手続きかと思いますので、分かりやすく、スムーズに対応できるよう、
また、当方自身も丁寧に業務を行えるように取り組んでいます。
もっとも、どの司法書士事務所でも同様の業務を行っている中で、自分がどこに依頼すれば良いのかという方もいらっしゃるかもしれません。
「①価格の安いところ」、「②近いところ」、「③実際会って相談できるところ」「④安心できるところ」「⑤早いところがいい」等々、いろいろな選び方があると思います。
これらは、全て正解だと思います。
①「価格が安い=ダメ」ではありませんし、「価格が高い=良い」とも限りません。
当然のことですが、「価格が安い」≒「その案件についやす時間や人、コストは小さい」はあるかと思います。
事務所ごとの努力はあるでしょうし、薄利多売のような形態をとっているかもしれません。
司法書士が手続きするならば、必ず最低限の仕事はしますし、間違ったことはしないでしょう。
ただ、対応時間が足らなければ、依頼者がサービスを受けたいと思っていたケアが抜けたり、ちょっと雑に感じる対応はあるのかもしれません。
個人的には、非常に高価であり、大切な不動産にそのような処理されるのは、嬉しくはありませんし、望みません。
ですので、弊所は、案件ごとに、一つずつ、ちゃんと対応したいので、弊所は最安値の事務所にはなりえません。
しかし、価格が高いほうの事務所でもないと、なんとなく、周りの話を聞いて感じてはいます。(自己評価ですが、、、)
堂々と「ボッタくり」と言われるような仕事はしていないことについては、自信をもって「大丈夫」と宣言できます。
とはいえ、相続登記の報酬って、実は、そんなに価格差が出ない分野の仕事なんですけどね。(各事務所の報酬の見方って分かりにくいですよね)
価格が分かりにくいのは、案件(不動産登記の状態、相続人の状況、対応する仕事量)ごとで、作業が大きく異なるからなんで、そのあたり、本当に難しいとも思っています。
②「近いところ」がいいは、もちろん。ただ、徒歩圏である必要はない。
事務所によっては、県外も受け付けますと宣伝しているところがあります。
これ、裏を返せば、会ってちゃんやり取りしてくれない、または、困ったときに来てくれないってことでもあります。
沢山不動産をもっていて、県外の山林もあるよという場合に、地域ごとに司法書士を分ける必要はないのですが、
いざというときに来てくれるというのは、意外と大切ですし、その司法書士の責任感の差を感じます。
そういう意味で、あんまり遠くの事務所には依頼しないほうがいいじゃないかなと思います。
(当方も、いくら気に入っていただいても、あまり遠方なら他の地域の信頼できる先生を紹介します。自分で対応できなくて、ちょっと残念だけど、、、)
③「実際会って相談できるところ」はそうすべきなんです。
司法書士の業務は、依頼者本人に会って、ちゃんと本人確認するのが原則です。
当然と言えば当然ですが、メールや電話だけで、他人の不動産の名義を変えてる先生って、怖いですよね。
自分の不動産を他人が勝手に名義変えていたら、、、(まぁ、ニュースになりますけど)
そんな心配がないように、これは業界として、面倒であっても、ちゃんとやっていくべきことなんだと思っています。
あと、今回の相続登記をきっかけに、会って、話して、依頼者さんの不安や心配を解決、または気付きや対応のアイデアにできるのは、チャンスだと思っています。
大切な不動産ですから、権利関係のメンテナンス、ちゃんとやっておきましょう!
④「安心できるところ」が当然かつ、一番だと思う。
専門家に合って、説明を聞いて、要望を伝えて、不安になったら意味がない。
また、何か問題があり、対応すべきことがあるのに、教えてくれなければ、それは専門家とはいえない。
弊所は、安心のために存在する、予防法務の専門家ですので、それに対する対応は惜しみません。
もちろん、手続きが終わった後も、弊所のお客様ですので、相続登記に限らず、なんでも気軽に相談した頂ける、身近なリーガルパートナーとして活用して欲しいと思っています。
ここ、自信があります!
⑤「早いところがいい」は、事務所によって差が出るかも。
これは、最低限、法務局に申請してから、手続き処理が終わってくる時間は、どこでも同じです。
ただ、申請するまでのスピードや、相続登記後に対応する予定の処理に合わせたスケジュールができるかは、事務所によって異なるでしょう。
この辺りは、普段から、不動産売買の絡んだ取引が多い弊所では、申請まで比較的短期間で業務を行えていると考えています。(これも自己評価ですね)
不可能を可能にするなんてことは言いませんし、そんなことできませんが、しっかり、ちゃんと対応していけば、自ずと遅延は致しません。
誠実に仕事をして、正々堂々と、最大限のスピードを尽くした結果を依頼者の皆さんに還元できるよう努めています。
いろいろ長文になってしまいましたが、不動産登記だと思うから感覚が分からないのかもしれません。
イメージするならば、自動車の車検に近い選び方なのかもしれませんね。
安いばかりの修理工場の車検に愛車を出したくない(トラブルや事故とか起こったら不安)というのと同様に、
皆さんのライフスタイルや、価値感、安心につながる相続登記手続きの一助になれるように努めていければと思っています。
と、言うわけで、せっかくご依頼を頂けるならば、司法書士法人浅井総合法務事務所まで、お気軽にお電話、メール、LINE(事務所公式アカウント)等を頂ければ嬉しい限りです。
ちなみに、概算の見積には「不動産の情報(場所や地番・家屋番号)」「固定資産税評価額(評価証明書や納税通知書)」「相続人の関係」が必要になります。
もちろん、ないと相談を受けないとは言いません(が、見積もりは後出しになっちゃいますので、その点は、ごめんなさい。)
どちらにしろ、最終的には、聞き取りをしっかりして、こちらで調査しなければ見積もりは確定しないのは、こちらも車検と似た感じですね。
でも、そこは誠実に、必要な費用はちゃんと説明し、節約できるところも、できるだけアドバイスしたいなと思います。
なんだか熱い営業ブログになってしまいましたが、たまには、良いですよね??
今、誰かの欲しい情報に繋がってくれていれば幸いです。
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階
司法書士法人
浅 井 総 合 法 務 事 務 所
社会保険労務士・行政書士
浅 井 総 合 法 務 事 務 所
電話052-508-7373
司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司